
D2C(Direct to Consumer/ダイレクト トゥ コンシューマー)というビジネスモデルがアメリカで注目され始めてから約15年、日本でもこの10年で急速に普及してきました。
D2Cとは、一般消費財メーカーが自社の商品やサービス(以下「商材」)を、中間業者を介さず、消費者へ直接届ける直販の形態です。しかし単なる「直販」とは異なり、商材の企画・製造・販売、そして購入後のコミュニケーションまでも自社で一貫して担う点が大きな特徴です。
このモデルの本質は、企業やブランドが伝えたい価値や世界観に共感してもらうことで、顧客との深い関係性を構築し、商材を長く愛用してもらうことにあります。大量販売よりもロイヤルティ重視という意味で、D2Cはまさに顧客との“継続的なつながり”を前提としたビジネスと言えます。
近年では、アパレル・化粧品・食品など多様な業種・規模の企業がD2Cに参入、あるいは参入を検討しており、私たちフュージョンにもご相談をいただく機会が増えています。
本コラムでは、そうした“知っているようで意外と知らない”D2Cについて、一見よく似ているメーカー直販との違いを整理しながら、D2Cの本質や背景、そしてCRM視点で見るそのビジネスモデルについて、分かりやすく解説していきます。
メーカー直販とは?従来型流通との違いを整理する
消費財が消費者の手に届くまでの流通経路は、従来、メーカー(製造事業者)→卸売事業者→小売店→消費者という「多段階の商流」が一般的でした。

それぞれのプレイヤーは独立した企業であり、自社の役割を果たすために、営業・在庫管理・物流・情報管理・経理など、必要な機能を自社内に保持して事業を展開しています。
一方、「メーカー直販」はこの商流をショートカットし、製造から販売までを一貫して自社で担うモデルです。つまり、製造業で必要とされる機能と、小売業で必要とされる機能をすべて1社で抱えることになります。
当然ながら、これは並大抵のことではありません。
商品を企画・製造するための“モノ”のリソースに加え、それを運用・販売していくための“人材”、そしてそれらを支える“資金”が揃ってはじめて成り立つ、いわば資本力が前提のビジネスモデルです。
実際、メーカー直販が一般化したのは1980年代以降とされており、当時から2000年代にかけては、IT製品やアパレル、化粧品、食品などを扱うグローバル企業や大手国内メーカーが主導してきました。
日本でも、アパレル大手や飲料メーカーの専業子会社、あるいは直販特化の通販企業など、資本やリソースを集中投下できる限られたプレイヤーだけが実践できるモデルだったのです。
D2Cを可能にした4つの進化──ビジネスの構造が変わった理由
これまでメーカー直販は、大手企業や専業プレイヤーにしか手が届かない、いわば“選ばれし者のビジネスモデル”でした。
ところが2000年前後から、いくつものテクノロジーやサービスの進化が重なり、この構図が大きく変わり始めます。
とくに次の「4つの機能の進化」は、D2Cという新たな潮流を生み出す土壌となりました。
1.販売機能の進化:誰でもオンラインで「お店」が持てる時代に
1990年代、楽天市場やYahoo!ショッピング(日本)、eBay(アメリカ)など、インターネット上に販売チャネルを提供するECプラットフォームが登場。さらに2000年代にはShopifyのような“誰でも自社ECを開設できる”ツールが普及し、販売のハードルは一気に下がりました。
マーケットプレイス型のサービスも充実し、中小企業でも安価に・簡単に・スピーディに、販売の基盤を持てるようになったのです。
2.マーケティング機能の進化:広告とメディアの民主化
2000年代中盤から、SNSの普及とともにデジタル広告市場が急拡大。以前は高コストゆえに大手しか使えなかったマスメディア広告が、誰でも手軽に活用できるデジタルメディアに置き換わっていきました。
Instagram、Facebook、YouTubeといったソーシャルメディア、さらにはオウンドメディアも活用され、「広告=高額」という常識が覆されたのです。マーケティングの外注化も進み、MaaS(Marketing as a Service)という支援形態も登場しました。
3.情報基盤の進化:クラウドで業務もDXも加速
以前は、情報基盤(業務システム)を自社で持つ「オンプレミス型」が一般的で、導入・運用・セキュリティ管理も一苦労でした。
しかし2010年代に入ってからは、クラウド上で提供されるSaaS(Software as a Service)が主流となり、マーケティング、受発注、在庫、物流、顧客管理などの機能を中小企業でも柔軟に使えるようになりました。
この情報基盤の進化が、D2Cの“自社完結”体制を現実のものにしています。
4.製造機能の進化:アウトソーシングでモノづくりの壁が低く
製造業では、1960年代からOEM(Original Equipment Manufacturing)による生産委託が広がっていましたが、2000年代以降はODM(Original Design Manufacturing)も一般化し、化粧品や食品といったBtoC商材でも活用が進みました。
これにより、単なる大量生産だけでなく、品質向上や新商品開発までも外部の力を借りて実現可能に。D2Cを志す企業でも、自社に製造機能がなくても“作れる時代”になったのです。
このように、販売・マーケティング・情報基盤・製造という4つの機能が進化したことで、かつては資本力のある企業しか展開できなかったメーカー直販の世界に、中小事業者も参入できるようになりました。
それが、D2Cというモデルの急速な広がりにつながったのです。
D2Cとメーカー直販の違いとは?顧客戦略で見えてくる本質
以上4つの機能が進化したことで、誰もがメーカー直販に挑戦できる環境は整いました。
しかし、それだけでD2Cが生まれたわけではありません。
D2CをD2Cたらしめているのは、“思想”と“顧客との向き合い方”の違いにあります。
D2Cの最大の特徴は、顧客との直接的なつながりです。
流通業者を介さずに商材を届けるため、顧客の声や反応をリアルタイムで受け取り、それをもとに商品やサービスを改善することが可能です。市場の変化にも迅速に対応でき、柔軟な意思決定ができるという強みがあります。
また、顧客との関係がデータとして蓄積される点も重要です。
購買履歴や行動データなどのファーストパーティデータを自社で収集・分析することで、One to OneマーケティングやCRMツールの運用が可能になります。
これにより「見込み客を獲得して売って終わり」ではなく、「既存顧客と長期的に関係を深めていく」ことが、ビジネスの軸になります。
さらにD2Cでは、自社のブランドの世界観や価値観を直接発信できるというメリットもあります。
ECサイトやSNSを通じて、企業のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)や開発ストーリー、プロダクトへの想いなどを自由に表現できます。
このストーリーテリングを通じて、商材を“買ってもらう”だけでなく、“共感し応援してもらう”というブランド体験へと昇華できるのです。
こうして見てくると、「D2Cもメーカー直販の一形態なのでは?」と思われるかもしれません。
確かに構造は似ていますが、最も大きな違いは“新規獲得”の考え方にあります。
メーカー直販企業の多くは、豊富な資本力を背景にマス広告で広くリーチし、大量の新規顧客を一気に獲得します(=アクイジション重視)。
一方D2Cは、広告費に限界がある前提で、一人ひとりの顧客に長く愛用してもらうこと(=リテンション重視)でビジネスを成立させます。
この違いは、マーケティング戦略や顧客との関係性、さらにはビジネス指標にまで及びます。
| メーカー直販 | D2C | |
| 参入企業 | 大手企業の事業部、通販専門子会社、通販事業企業 | 中小企業、地場企業、スタートアップ |
| 提供する商品・サービス | 既存ブランド、既存商材 | 専用ブランド、専用商材 |
| 主要な施策 | 新規顧客向けを重視 | 既存顧客向けを重視 |
| 活用メディア | マス広告が中心 | デジタル広告が中心 |
| ターゲットオーディエンス | マス | ニッチ、ファン |
| 目指す顧客との関係性 | 単発、取引ごと | 長期的、継続的なエンゲージメントを結ぶ |
| 重視する点 | 品質、機能、価格 | ブランドの世界観、ストーリー、顧客体験 |
このように、D2Cとメーカー直販は似て非なるもの。
その違いを正しく理解することが、D2Cビジネスを成功に導く第一歩となります。
D2Cの立ち上げ・見直しに向けて──次の一歩はCRM戦略の整理から
今回はD2Cの基本を整理する第一歩として、「D2Cとは何か」「メーカー直販との違い」「その背景にある機能進化」についてお伝えしました。
ビジネスモデルの構造や考え方の違いを理解いただくことで、D2Cという言葉に対するモヤモヤが少しでも晴れたのではないでしょうか。
とはいえ、実際にD2Cを始めようとすると、
- どのような顧客体験を設計すればいいのか?
- 自社にとって最適なCRM施策は何か?
- どこまで自社で対応し、何を外部に任せるべきか?
といった、実務的な課題に直面する方も多いはずです。
フュージョン株式会社では、30年以上にわたり、BtoCビジネスにおけるCRM戦略立案から実行支援までを一貫してサポートしてきました。
とくにD2Cにおいては、「顧客との関係性づくり」に直結する顧客戦略策定支援やデータ分析、シナリオ設計、コミュニケーション施策の実行支援まで、現実的かつ成果につながるご提案が可能です。
まずはお悩みレベルで構いません。
以下のフォームより、お気軽にお問い合わせください。


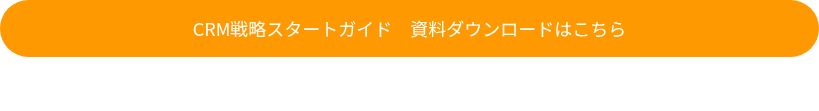
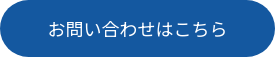
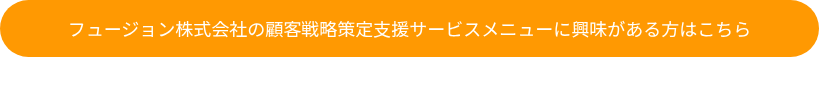


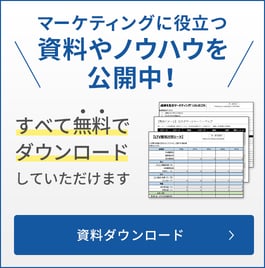



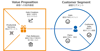




%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png?width=100&height=60&name=%E3%80%90%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BE%8B%E4%BB%98%E3%80%911%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%8B!%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(CJM)%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png)




