
マーケティング活動の費用対効果を説明するうえで欠かせない指標が「ROI(投資利益率)」です。
しかし、広告やキャンペーンのROIは算出できても、メールやLINE、DMなどのCRM施策になると「効果を数字で示しづらい」と感じている担当者も多いのではないでしょうか。
マーケティング活動の効率を評価するKPIとして「Return on Marketing Investment」(以下、ROMI)が挙げられます。
今回のコラムでは、主に
- ROMIとROIの違い
- ROMIの基本的な算出方法
- BtoCマーケティングにおける実践活用のポイント
を整理しながら、CRMデータを活用してROIを高めるヒントを紹介します。
ROIでは見えない「マーケティング投資の本当の効果」
多くの企業では、広告費やキャンペーン投資の成果をROI(投資利益率)で評価しています。
ROIは「どれだけの費用で、どれだけの利益を生み出したか」を明確に示すシンプルな指標で、経営判断の根拠として非常に有効です。
しかし、このROIだけでは、マーケティングの本当の効果を捉えきれない場面が少なくありません。
たとえば、BtoC企業では次のような課題がよく見られます。
- 広告施策はROIを算出できるが、CRM施策(メール、LINE、DMなど)は効果が数字で見えにくい
- 新規獲得キャンペーンは評価されやすい一方で、リピート促進施策の貢献が軽視されてしまう
- ブランド認知や顧客満足など、売上以外の価値が可視化されていない
これらは、ROIが「短期的な売上に紐づく効果測定」を前提としていることが大きな原因です。
一方、実際のマーケティング活動は、新規顧客の獲得から育成・再購入・ファン化まで、時間軸を伴うプロセスで成り立っています。
したがって、マーケティング投資の成果を正しく評価するには、単発の費用対効果だけでなく、顧客行動全体における投資効果を捉える視点が必要です。
このような課題を解決するために使えるのが、マーケティング領域に特化した指標「ROMI(Return on Marketing Investment)」です。
以降では、このROMIの定義とROIとの違い、そしてBtoC企業における活用のポイントを解説します。
マーケティングROI(ROMI)とは?ROIとの違いと基本の考え方
マーケティングROI(ROMI:Return on Marketing Investment)とは、マーケティング活動によって生み出された成果を投資コストで割ることで、マーケティング投資の効率性を示す指標です。
ROI(Return on Investment)は、事業への投資とその投資から得られる収益の収益率を測る金融指標であるのに対し、ROMIは特定、または全てのマーケティング活動への投資と、その投資から得られる収益の収益率を示すマーケティング指標です。
簡単に言えば、マーケティングキャンペーンやプログラムなどの施策にかけたコストと、その施策から得られる売上を基に算出される収益率(%)を用いて、施策の効率や成果を評価する指標となります。
ROI: 投資全体の利益率
ROMI: マーケティング施策の利益率(販促・広告・CRMなどの費用対効果)
ROMIの計算式
ROMIの計算式はシンプルで、投資(マーケティングコスト)と収益(マーケティングによる売上増加額)を用いて次のように示すことができます。
ROMI(%)=(マーケティングによる売上増加額 − コスト) ÷ コスト × 100
この式は、マーケティング活動が生み出した“純粋な利益”が、投下したマーケティングコストの何%に相当するかを示しています。
売上「増加額」を使う理由
ここでのポイントは、「売上全体」ではなく「マーケティングによる増加額」を使う点です。
ROMIは「マーケティングを実施したことで、通常よりどれだけ売上が増えたか」を測る指標のため、もともとマーケティング投資をしなくても発生していた売上(ベースライン)は対象に含めません。
(例)
|
状況 |
売上 |
増加額 |
コスト |
ROMI |
|
施策実施なし |
1,000万円 |
— |
— |
— |
|
施策実施あり |
1,200万円 |
+200万円 |
50万円 |
(200−50) ÷ 50 ×100=300% |
この場合、施策によって得られた「200万円の増加分」がマーケティングの成果であり、そのため売上増加額からコストを引くことで「純粋な利益=リターン」を算出します。ここで、単純に「売上全体 − コスト」で計算すると、マーケティングを実施しなくても発生する通常売上が含まれてしまい、施策の貢献度を正確に評価できないので注意が必要です。
より正確なROMIは粗利益増加額で算出を
売上ベースのROMIは手軽で計算しやすいですが、原価率の違いを無視するため、実態より高く(または低く)見えてしまうことがあります。より正確に投資効率を評価するには、売上ではなく「粗利益(貢献利益)の増加額」を用いて算出すると良いでしょう。
ROMI(%)=(増分粗利益 − マーケティングコスト) ÷ マーケティングコスト × 100
※増分粗利益 =(施策実施時の売上 − ベースライン売上)× 粗利率
※「ベースライン売上」は、施策を行わなかった場合に想定される売上で推定
粗利益ベースにすることで、商品・カテゴリごとの原価差や、CRM施策の中長期の利益貢献を反映できます。数値は%で表され、プラスで大きいほど投資効率が高いことを示します。
(マーケティング施策コスト100万円の場合の例)
|
指標 |
数値 |
備考 |
|
施策コスト |
100万円 |
広告費・コンテンツ制作費など |
|
売上増加額 |
300万円 |
キャンペーン効果による |
|
商品粗利率 |
40% |
原価60% |
この場合のROMIについて、算出ベース別に見ると以下のような結果になります。
|
算出ベース |
式 |
ROMI算出結果 |
|
売上ベースROMI |
(300−100) ÷100×100 |
200% |
|
粗利益ベースROMI |
(300×0.4−100) ÷100×100 |
20% |
こう見ると、粗利益ベースのROMIが最も正確ですが、実務上は商品原価をマーケティング施策単位で把握できないケースも多くあります。
そのため、短期施策の評価や部門内の比較には売上ベースのROMIでも十分有効です。重要なのは、同じ指標定義で継続的に効果を比較・改善することです。
ROMIの値の意味としては、以下のように捉えられます。
- ROMIがプラス(>0%):投資によって得られた利益がコストを上回っている
- ROMIがマイナス(<0%):投資に対して利益が出ていない(改善が必要)
ROMIが高い施策ほど「費用対効果が高く、再投資する価値がある」と判断できます。そして、複数の施策を比較して、どこにコストを重点配分すべきかを判断するための指標として活用できます。
ROMIを通して、自社が投じたマーケティングコストがどのくらいのリターンを生み出したのかが明確になります。これにより、キャンペーンの成功度や、特定の期間にわたるマーケティング活動の効率を評価できます。
ROMIの実践的活用:短期・中長期の指標としての利用
ROMIは「マーケティング投資の成果を数値で評価する指標」ですが、その活用方法は目的や期間によって異なります。
ここでは、短期的な評価と中長期的な改善の両面から、実務での活用ポイントを整理します。
短期的な指標としてのROMI活用
短期的には、施策単位での投資効率を測る指標としてROMIを使います。
例えば次のようなシーンです。
- 新規獲得キャンペーンの費用対効果を測定する
- メール、LINE、SNS広告などチャネル別のROMIを比較する
- クリエイティブや配信タイミングなど、ABテストの成果を確認する
このような使い方では、ROMIはマーケティングの即時的な反応効率を判断するための指標になります。
BtoC企業の場合、広告やキャンペーンのROMIを定期的に可視化することで、次回の配信設計やコスト配分の最適化に役立ちます。
ただし、短期的な数値のみに注目しすぎると、「ROMIを上げるために投資を抑え、結果的に売上全体が下がる」といった逆効果に陥るリスクがあります。
ROMIは効率を示す指標であって成果の総量を示す指標ではないため、他のKPI(売上・新規顧客数・LTVなど)とあわせて総合的に判断することが重要です。
中長期的な指標としてのROMI活用
一方で、中長期的な指標としてROMIを活用する場合、四半期や1年といった一定期間におけるマーケティング全体の投資判断を見直す指標として活用できます。
BtoC企業では、
- 短期的なキャンペーンROI(アクイジション指標)
- 中長期のCRM ROI(リテンション指標)
の2層でROMIを見ていくことが効果的です。
これにより、「短期的な売上効率」と「中長期的な顧客価値拡大」の両方をバランスよく改善できます。
ROMI活用時の注意点と課題
ROMIはシンプルな計算式であるがゆえに、定義や前提条件が曖昧なままだと数値の信頼性が大きく揺らぎます。
特に次のような点には注意が必要です。
- どのコストをマーケティング投資として含めるか
- 複数チャネルの売上をどのように分配・評価するか
- 期間中の外的要因(価格変更、在庫、天候など)をどう補正するか
マーケティングコストには、広告費や制作費のような直接的コストだけでなく、
システム利用料や人件費、店舗運営費などの間接的コストも含まれる場合があります。
これらをどこまで含めるかによって、ROMIの数値は大きく変動します。
また、売上についても、キャンペーンの直接成果だけでなく、Eメール、LINE、SNSなど複数のチャネルを経由した間接貢献をどう扱うかが課題です。
アトリビューション分析などで貢献度を推定する方法もありますが、全ての売上を施策単位で厳密に割り振るのは現実的ではありません。実務上は、CRM/MAツールなどで簡易的なアトリビューションモデル(線形配分やU字モデルなど)を使い、一定のルールで貢献度を暫定的に割り振るケースが多く見られます。
こうした方法でも十分に傾向を把握できるため、完璧な数値化よりも、社内で一貫した基準を持つことが重要です。
こうした基準を事前に明確にし、関係者間で共有しておくことで、ROMIを施策比較や次期戦略立案に活用しやすくなります。また、BtoCのCRM施策のように、複数施策が連動して効果を生むケースでは、「施策単位」よりも「顧客単位」でROMIを評価するほうが実態を反映できます。
フュージョン株式会社では、マーケティング施策の効果検証に関する基本的な解説記事も公開しています。ご興味のある方はあわせてご一読ください。
もし、こうした評価ルールの設計やデータの整理を社内だけで進めるのが難しい場合は、第三者の視点でフレームを整えるのもひとつの方法です。CRMデータを軸にしたROI可視化やアトリビューション設計の支援を行うパートナー企業を活用することで、運用の負荷を抑えつつ精度を高めることができます。
フュージョン株式会社では、ROMI改善に直接関係する事例だけでなく、CRMやLTV向上施策に関わる幅広い支援実績があります。詳しくは事例集をご覧ください。
ROMIを改善する3つの視点:新規・リピート・LTV
ROMIを継続的に改善していくには、単発の施策評価だけでなく、顧客との関係性のフェーズに応じて投資効果を見直す視点が重要です。
BtoC企業では、マーケティング活動を大きく次の3つのステージに分けて考えると、ROMIをより正確かつ戦略的に高めることができます。
1.新規顧客の獲得効率を高める
新規獲得施策では、広告・キャンペーンなどアクイジション活動の費用対効果を明確にすることが第一歩です。
- 広告チャネルごとのROMIを算出し、効率の高い媒体へ再配分する
- クリックやコンバージョン率といった中間指標に頼りすぎず、「売上増加額ベース」で評価する
- クリエイティブやターゲティングの改善によってROMIを継続的に向上させる
短期的なROMI改善は比較的測りやすい領域ですが、顧客の獲得単価(CPA)や平均購入単価など、他のKPIと併せて総合的に判断することがポイントです。
2.既存顧客のリピート率を高める
CRM施策においては、「再購買・再来店・アップセル」の投資効率を見える化することが重要です。
BtoCのCRM施策は、メール・LINE・DM・アプリ通知など複数チャネルが連動するため、個別施策のROIよりも顧客単位でのROMIを捉える視点が欠かせません。
- セグメントごとにROMIを算出し、どの顧客層が高効率かを把握する
- 再購買率や平均購入間隔など、行動指標を含めたROMI改善を行う
- アトリビューション分析を活用し、複数施策の“間接貢献”を補正する
こうしたCRM領域でのROMI改善は、短期的売上だけでなくLTVの向上にも直結します。
HubSpotなどのMA/CRMデータを活用すれば、顧客単位で施策効果を可視化しやすくなります。
3.顧客生涯価値(LTV)視点でのROMI改善
最後の視点は、LTV(Life Time Value)=顧客生涯価値を軸にした中長期のROI評価です。LTV視点では、「一人の顧客が将来的にどれだけの利益をもたらすか」をもとに、マーケティング投資の先行効果を測定します。
短期的なROMIが低く見える施策でも、長期的に高いLTVを生む場合は投資価値が高いと判断できます。
例えば、あるキャンペーンの短期ROMIが20%と小さくても、その施策で獲得した顧客が高いリピート率を示し、平均LTVが高ければ、LTVベースのROMIは80%以上に上昇するケースもあります。
このように、短期の効率だけで判断せず、顧客との関係を通じた長期的な利益貢献を評価することが重要です。
LTVベースでのROMI評価では、次のような観点が効果的です。
- 獲得時点のROMIが低くても、LTVを加味すれば黒字化するケースを見極める
- CRM・サブスクリプション型ビジネスでは、顧客維持コスト(リテンションコスト)を含めて評価
- 顧客セグメント別にLTVベースのROMIを比較することで、投資配分の優先順位を明確にする
実務上は、LTVベースのROMIは短期では変動しにくいため、四半期単位でモニタリングし、トレンドを確認する運用が効果的です。モニタリング用レポートをもとに、投資配分やCRM施策の方向性を見直すことで、ROIを単発指標ではなく「中期的な成長指標」として活用できます。また、LTVベースの評価を行うには、CRMや購買データを整理し、顧客単位で売上・利益を追える仕組みが必要です。
社内でのデータ整備が難しい場合は、外部パートナーと定期的にレポートをレビューしながら分析設計を進める方法もあります。
ROIを「数字」から「顧客理解」へ進化させよう
ROIやROMIは、単なる“数字の成果”を測るための指標ではありません。
マーケティング施策を通じて、顧客との関係をどのように深め、どれだけの価値を生み出しているかを見える化するためのものです。
BtoC企業では、新規顧客の獲得ROIに加えて、CRM施策によるリピート促進やLTV向上といった中長期の投資効果を正しく評価することが重要です。
ROIを“短期的な効率”だけで捉えるのではなく、顧客視点での価値蓄積を示す指標として再定義することで、マーケティング活動全体がより持続的な成長へとつながります。
また、ROMIを正しく活用するには、コスト定義や期間設定、データの統合といった分析の前提を整理する必要があります。
特に複数チャネルが連動するCRM施策では、施策単位ではなく顧客単位でROIを見直す発想が欠かせません。
自社内でこれらを仕組み化するのが難しい場合は、第三者の視点でデータ整理や効果測定のフレームを整える方法も有効です。
フュージョン株式会社では、CRMデータを軸にしたROI可視化やLTVベースのROI改善など、クライアント企業の実情に合わせた可視化・分析支援を行っています。お悩みのある方は、お気軽にお問い合わせください。




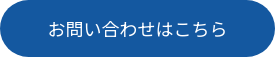


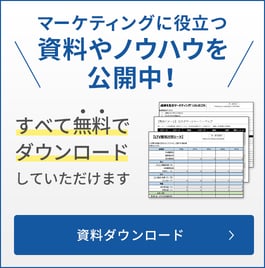



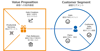




%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png?width=100&height=60&name=%E3%80%90%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BE%8B%E4%BB%98%E3%80%911%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%8B!%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(CJM)%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png)




