
D2C(Direct to Consumer/ダイレクト トゥ コンシューマー)は、メーカーやブランドが自社のECサイトなどを通じて直接消費者に販売するビジネスモデルです。
今回のコラムでは、大企業や中堅企業でD2Cに取り組もうとしているマーケティング担当者の方や、すでに取り組んでいる方々に向けて、以下の3点を中心に解説します。
- D2Cのメリット・デメリット
- D2Cに向いている商材の特徴
- D2Cを成功させるために重要なKPI(LTVとCPO)
なお、そもそもの「D2Cの成り立ち」や「メーカー直販との違い」については、以下の記事で解説しています。
まだお読みでない方は、ぜひご覧ください。
D2Cのメリット・デメリットを整理する
D2Cにはメリット・デメリットがそれぞれあります。代表的なものについて見ていきましょう。
D2Cのメリット
一般的には、D2Cには以下のようなメリットがあります。
- 高い収益性
商流における中間マージンが発生しないため、利益率を高めやすい - 顧客データの取得と活用
顧客の属性、購買履歴、行動履歴などのデータを直接取得でき、分析結果を商品開発やマーケティングに反映できる - ブランド力の強化
企業の価値観や世界観を直接伝えることで、顧客の共感を得てブランドロイヤルティを築きやすい - 迅速な商品開発と改善
顧客からのフィードバックを直接得られるため、ニーズに即した改善・新商品開発がスピーディーに可能 - 販売戦略の自由度
自社主導で販売量・価格設定・プロモーションを柔軟にコントロールできる
最大のメリットは「自社で顧客接点と事業全体をコントロールできる点」です。
ただし、メリットで挙げた「顧客との関係構築」は実際には“前提条件”であり、これが実現できなければリピート購入やファン化にはつながりません。
D2Cのデメリット
一方で、D2Cには次のようなデメリットもあります。
- 高いコスト負担
自社でECや基盤を構築・運営するため、初期投資・広告宣伝・顧客維持の費用がかかる - ブランド認知に時間がかかる
ゼロからブランドを立ち上げる場合、ブランドや商材の認知度を高めるまでに時間とコストがかかる - 集客の難しさ
自社ECには大手ECモールのような集客力がないため、自社で積極的に広告やSNSを活用して顧客を獲得する必要がある - 物流・カスタマーサポートの負担
発送や顧客対応を自社または外部委託で整備しなければならない - ビジネスとしての総合力が問われる
資金力、商品力に加えて、ブランディング・マーケティング・顧客対応・物流など幅広い体制が必要
デメリットの本質は「コスト負担」と「体制構築力」に集約されます。
ただし、これらはD2Cに特有というより、多くの新規事業に共通する課題です。
解決のポイントは、すべてを内製化しようとせず、自社で持つべき機能/外部に委託すべき機能を見極めることにあります。
特に製造や小売の機能を自社に持つケースが多いD2C企業では、物流・決済・顧客コミュニケーションなどを外部パートナーと連携することで、効率的な事業拡大が可能になります。
■D2Cのメリット・デメリット比較まとめ(一覧表)
| 観点 | メリット | デメリット |
| 収益性 | 中間マージンがなく利益率を高めやすい | 初期投資や広告・運用コストが大きい |
| 顧客データ | 属性・購買履歴・行動履歴を直接取得し活用できる | データを活かす分析・運用体制が必要 |
| ブランド構築 | 世界観を直接伝え、ファンを獲得しやすい | ブランド認知に時間とコストがかかる |
| 商品開発・改善 | 顧客フィードバックを即座に反映できる | 継続的に体制を維持するリソースが必要 |
| 販売戦略 | 価格・プロモーションを自由にコントロール可能 | 集客はすべて自社努力で行う必要がある |
| 事業運営 | 顧客接点を自社でコントロールできる | 物流・サポート・決済など総合力が問われる |
D2Cに向いている商材とは? 成功する商品の特徴を解説
次に、D2Cビジネスに適した商材の特徴を整理します。
一般的にD2Cに向いているとされるのは、次のような条件を持つ商材です。
【機能的な特徴(実用面)】
| 1.一般消費財であり、日常的に使われる 2.購入単価が高すぎない 3.継続的に使用・購入される |
【感情的な特徴(共感・体験価値)】
| 4.他社にない独自性やストーリーを持つ 5.使い続ける理由がシンプルで明確 6.価格以上に「体験価値」を提供できる(単なる機能提供にとどまらない) |
D2Cの成功には、この機能的な特徴に加え、競合との差別化につながる感情的な特徴を持てるかどうかが重要です。
逆に、1〜3の条件しか持たない一般消費財は、大手ナショナルブランドや低価格のプライベートブランドには競争で勝てません。
だからこそ顧客に「なぜこの企業から買うのか」「なぜこの商材を選ぶのか」という明確な理由を提供する必要があります。
この理解と共感が継続購入につながり、最終的に企業のゴールであるLTV(顧客生涯価値)の最大化を実現します。
D2Cビジネスでの留意点:LTVとCPOの関係を理解する
最後に、D2Cビジネスを進めるうえで重要な指標について整理します。
D2Cは製造小売業の一形態であり、メーカー直販と大きく異なるのは新規顧客の獲得に投資できる費用構造です。
ただし「コストをかけられるかどうか」に関わらず、新規顧客を集客しなければならない点は共通しています。
D2Cでは次の2つのKPIを押さえることが重要です。
- LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)
顧客が生涯を通じて企業にもたらす利益の総額 - CPO(Cost Per Order:1注文あたり獲得コスト)
新規顧客1人を獲得するために必要な広告・販促などの総コスト
メーカー直販とD2Cの違い
そしてメーカー直販とD2Cでは、これらLTVとCPOの関係性が異なります。
メーカー直販(単発購入型)
継続購入を前提としないため、CPOが小さければ粗利が大きく、逆にCPOが大きくなれば粗利が小さく、時にはマイナスになります。
そのため、以下2点がポイントです。
・「CPOが想定コスト内に収まっているか」がKPIの中心
・LTVという概念はほとんど使われない
D2C・メーカー直販(継続購入型)
継続購入を前提とするため、
・「LTV > CPO」を実現できるかどうかがゴール
・初回購入で達成できるのが理想だが、多くは複数回の継続購入によって関係を築く
D2Cの場合、実務上は一定期間で区切ったLTVや、このLTVを達成するための購入回数や期間をKPIとして採用するケースが多いです。
D2CでKPIを設計する際は、以下の点を意識することが重要です。
- LTVとCPOのバランスを常にチェックする
- 「何回の購入でLTV>CPOを達成できるか」を明確にする
- CPOを下げる施策(広告効率化、紹介制度、オウンドメディアなど)とLTVを高める施策(リピート促進、ロイヤルティ施策、CRM活用)を組み合わせる
LTVとCPOのバランスを設計するには、CRM戦略の全体像を整理することが不可欠です。
フュージョンでは、はじめてCRMに取り組む企業や、すでに実施している施策を見直したい企業に向けて、「CRM戦略スタートガイド」をご用意しています。
- CRMの基本概念と重要性
- 取り組みを進めるステップ
- 成功事例とKPI設計のポイント
といった内容をまとめており、自社のCRMの現状を棚卸し、LTV最大化に向けた次のアクションを考えるヒントになります。貴社の取り組みにご活用ください。
D2Cの成功はビジネスモデルの理解にある
今回のコラムでは、
- D2Cのメリットとデメリット
- D2Cに適した商材の特徴
- KPI(LTVとCPO)の関係と留意点
について整理しました。
参考コラム「D2Cとは?メーカー直販との違いとCRM視点で読み解くビジネスモデル」とあわせてお読みいただくことで、D2Cビジネスの全体像をより深く理解いただけたのではないでしょうか。
身近になったとはいえ、D2Cは「商品を売るだけ」では成立しません。
ブランド戦略、顧客データ活用、ロイヤルティ設計、物流やサポートまで、幅広い機能とそれを運用する人材・スキル・コストが求められる、総合力が試されるビジネスモデルです。
すでにD2Cを実践しているが成果に課題を感じている方、これから参入したいが「どこから手を付けていいかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
フュージョン株式会社は30年以上にわたり、さまざまな業界・業種でCRM戦略の策定から施策の実行・運用までをワンストップでサポートしてきました。
特にD2C領域においては、
- 顧客戦略の策定支援
- 顧客データ分析サービス
- KPI設計と継続購入を前提とした顧客ロイヤルティ向上施策
- CRM/MAを活用したコミュニケーションプログラム設計・運用
などを通じて、現実的かつ成果につながるマーケティング施策をご支援しています。
D2Cに関して課題やお悩みをお持ちの担当者様、まずはお気軽にご相談ください。


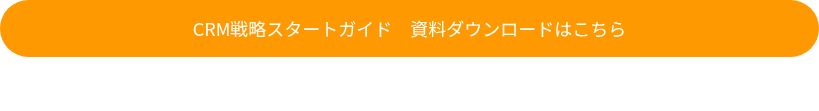
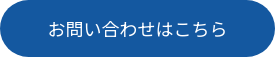


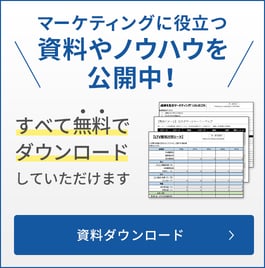



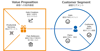




%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png?width=100&height=60&name=%E3%80%90%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BE%8B%E4%BB%98%E3%80%911%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%8B!%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(CJM)%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png)




