 国内市場の縮小や消費者ニーズの多様化により、小売業界はこれまで以上に「顧客との関係性」を重視した経営が求められています。
国内市場の縮小や消費者ニーズの多様化により、小売業界はこれまで以上に「顧客との関係性」を重視した経営が求められています。
新規顧客の獲得コストは既存顧客の5倍にのぼるとされるなか(1:5の法則)、既存顧客のロイヤルティを高め、生涯価値(LTV)を最大化することが成長戦略のカギとなります。
この記事では、小売業がCRM(顧客関係マネジメント)に戦略的に取り組む意義を整理し、戦略設計から実行・改善までのステップ、さらに実際の当社の支援事例を交えながら、持続的な成長のための道筋について解説します。
なぜ小売業にCRMが必要なのか?
小売業においてCRMが不可欠とされる背景には、次の3つの要因があります。
顧客獲得コストの高騰と既存顧客維持の重要性
新規顧客の獲得には既存顧客の5倍のコストがかかる「1:5の法則」や、顧客離脱率を5%改善すると利益が25%改善される「5:25の法則」が示す通り、既存顧客の維持こそ収益性に直結します。

国内市場や顧客ニーズの多様化に加え、特に小売業は競合が多く、近年は販促や広告費の高騰により新規獲得効率は悪化しやすい状況が起きています。だからこそ、既存顧客との関係性を深めるCRMの役割が大きくなっています。
会員プログラムやポイントプログラム施策が直面する課題
多くの小売企業が導入している会員カードやポイント制度も、ただ「貯まる・使える」という経済的価値や利便的価値の提供だけでは差別化が難しい時代です。
顧客データを活用して購買行動や心理ロイヤルティを理解し、心理的価値も含め一人ひとりに最適化した施策を届けなければ、顧客の会員プログラムからの離脱を招いてしまいます。
D2Cモデルとの接点
ECチャネルの拡大により、小売企業もD2C(Direct to Consumer)的な発想を持つ必要があります。D2Cは単なる「直販」とは異なり、商材の企画・製造・販売、そして購入後の顧客とのコミュニケーションまでも自社で一貫して担う点が大きな特徴で、CRMを軸に「なぜ今、この顧客に届けるのか」という顧客コミュニケーション設計が顧客体験の質を左右します。
このように、小売業でも店舗とデジタルの垣根を越えた顧客理解が求められています。
小売業CRMの基本ステップ
小売業におけるCRM戦略は、段階的に「現状把握としてCRM戦略の棚卸しを行い、あるべきCRM戦略を策定し、個別施策を実行・改善する」流れで進めることが重要です。
ここでは、3つのステップを整理します。

STEP1:現状把握
CRM戦略の出発点は、自社の取り組みを棚卸しし、課題を明確にすることです。
特に小売業における現状把握では、次の3つの軸を意識することが重要です。
① CRM戦略の有無や内容
- そもそも自社に「CRM戦略」や「ビジョン・ミッション」が明文化されているか。
- プログラム名や顧客への約束(バリュープロポジション)が定義されているか。
- 顧客別のペルソナやカスタマージャーニーを設計しているか。
戦略が曖昧な場合、施策は場当たり的になりやすく、中長期的なLTV最大化につながりません。
② CRM実行計画内容や施策設計
- KGI(例:会員売上比率向上)やKPI(例:F2転換率、アプリ利用率)が設定されているか。
- 短期〜中長期での数値目標やシミュレーションが存在するか。
- 各施策が「どの顧客段階を強化するのか」を整理できているか。
計画段階で顧客行動と指標を結びつけることが、施策効果を測定・改善する前提条件になります。
③ CRM実務レベルでの各施策の状況
- データ分析:購買履歴をRFM分析でセグメントし、優良顧客/休眠顧客など顧客セグメントの比率を把握できているか。
- プログラム運用:会員カードやアプリに基づくポイントプログラムに「ステージ制」や「利用頻度に応じた特典」などの仕組みを持たせているか。
- チャネル別成果:店舗販促とEC販促の費用対効果(ROMI)を比較し、施策ごとの効率を把握できているか。
- タッチポイント設計:メール、DM、アプリ通知、LINEなどのチャネルが顧客の購買ステージごとに適切に配置され連携が考慮されているか。
小売業ではID-POSデータが膨大に存在し、タッチポイントも複数ありますが、これらが「点」ではなく「線」でつながっていないと、顧客理解が不十分になり、施策効果を正しく測れません。
このように、3つの軸で現状を具体的に整理することで、戦略〜実務のズレを可視化でき、自社のCRM課題を明らかにできます。フュージョンでは、CRM現状セルフチェックシートを公開しています。まず簡易的に現状を整理したい方は、お役立てください。
STEP2:戦略策定
ここでは、STEP1での現状把握結果を踏まえ、あるべきCRM戦略を策定します。
「CRMは顧客と企業の関係性を深めてビジネスを成長させるための経営戦略のひとつ」と捉えると、以下の観点が重要です。
①顧客データの基礎分析
戦略策定の前提として、まず顧客属性・購買履歴・チャネル別の利用傾向などを整理し、「変化」や「違い」を把握します。
RFM分析やセグメント別の売上構成比、チャネルごとの購買頻度などの基礎分析を行うことで、戦略の土台となるインサイトを得られます。
なお、STEP1で既に十分な顧客データ分析やデータ活用状況が判明している場合は、その結果を用いても良いでしょう。
②カスタマージャーニーの設計
顧客が 認知 → 初回購入 → 継続購入 → ロイヤル化 へと進むプロセスを可視化し、各段階での課題を整理します。
店舗とEC、アプリなど複数チャネルでの顧客体験を統合的に捉え、「どこでつまずいているのか」を明確化することがポイントです。
フュージョンでは、カスタマージャーニー設計用テンプレートを公開しています。実際にカスタマージャーニーの設計に取り組む際にご活用ください。
③KPIの設定
カスタマージャーニーを設計したうえで、KPIは単なる売上目標ではなく、顧客行動に基づいた指標を設定します。
(例)会員化率、F2転換率、アプリ利用率、休眠会員復活率
KPIはKGI(例:会員売上比率30%向上)にひもづけ、施策ごとの改善対象を明確にします。
④長期的な育成シナリオの構築
CRM施策は単発ではなく、年間を通じた顧客育成シナリオとして設計します。
(例)春=新規会員獲得、夏=F2転換施策、秋=優良顧客イベント、冬=ロイヤルティ強化キャンペーン
ここでは、短期売上だけでなく、中長期での顧客育成を両立する顧客コミュニケーションの設計と個別施策の計画が求められます。

STEP3:施策実行と改善
STEP2で策定した戦略を、具体的な施策へと落とし込みます。小売業のCRMにおける施策実行は「一度やって終わり」ではなく、KPIに基づく効果検証と改善(PDCA)を繰り返すことで、顧客ロイヤルティを高めていくことが重要です。
① アクション設計と多様な施策の実行
CRM戦略を実行に移す際には、顧客ステージ(認知 → 初回購入 → F2転換 → 継続購入など)ごとに最適なアクションを設計することが不可欠です。以下は例としてご紹介します。
新規顧客獲得(アクイジション)施策
- マス広告やダイレクト広告で認知を拡大
- クーポンやオファー設計で初回購入を促進
- 媒体ごとの反応率を計測し、チャネル別の効果を比較
F2転換(顧客化)施策
- 初回購入者を次の購買へ導くため、アプリ通知やDMでのフォロー
- デジタルとアナログを組み合わせたクロスチャネル施策
- 顧客属性や購入商品に基づいたおすすめ提案
継続購入・ロイヤルティ強化(リテンション)施策
- 定期フォローや商品案内、ポイント付与による関係性の強化
- SNS・アプリでのコンテンツ強化による日常的接点の確保
- UI改善やWeb接客、ギフト提案でEC利用の利便性を向上
- 休眠顧客への掘り起こし施策や、優良会員向けの特典提供
このように、顧客セグメントに応じて「どのチャネルで」「どのタイミングで」「何を届けるか」を整理することが、実行フェーズの成否を決めます。

② 効果検証と改善
施策の実行時には、施策ごとにKPIを設定し、効果検証を見据えて結果を定量的に把握(例:DMのレスポンス率、F2転換率、アプリ利用率)するようにします。施策の成果を「仮説通りか/想定外か」で分析し、次の施策に反映していきましょう。
単発施策の積み重ねではなく、継続改善のサイクルとして運用することが重要です。
③ PDCAの仕組みづくり
CRM施策を持続的に成功させるためには、単発の取り組みで終わらせず、効果検証と改善を組織的に繰り返す仕組みを整えることが不可欠です。小売業では店舗・EC・アプリなど多様なチャネルが存在するため、効果検証もチャネルごとに分断せず、横断的に行う必要があります。
そのためには、営業・マーケティング・店舗運営といった部門がそれぞれのデータを共有し、共通のKPIに基づいて成果を確認する体制を築くことが大切です。たとえば、店舗の来店データとECの購買履歴を一元的に分析すれば、「アプリクーポンの利用が店舗購買にどう影響したか」といった洞察を得ることができます。こうした部門横断の知見が蓄積されることで、改善サイクルはより精緻に回せるようになります。
最終的には、顧客がどのチャネルを利用しても一貫した体験を受けられる状態をつくることが、ロイヤルティ向上とLTV最大化の近道となります。PDCAは単なる分析業務ではなく、組織全体で顧客体験を進化させ続けるための経営基盤と位置づけるべきです。
フュージョンではCRM戦略において、施策立案から戦略実行まで伴走してご支援をしています。これまで当社がご支援した小売業界向けの支援事例をご用意していますので、今後の施策のヒントとしてぜひご活用ください。
CRM成功のための重要ポイント
小売業でCRMを成功させるためには、単に会員制度やシステムを導入するだけでは不十分です。
真の成果を出すには、戦略と顧客理解を踏まえた運用が欠かせません。
ここでは、特に押さえるべき3つのポイントを解説します。
ポイント1:単なるシステム導入では不十分
「CRMツールを導入したから大丈夫」と考える企業は少なくありません。
しかし、システムはあくまで手段であり、導入だけでは成果は出ません。
CRMの本質は「なぜその顧客に、なぜ今アプローチするのか」という問いに戦略的に答えられるかどうかにあります。データを収集・管理するだけでなく、それを施策設計や改善サイクルに活かして初めて、売上貢献につながります。
ポイント2:顧客心理を理解した施策設計
データ分析による数値管理は重要ですが、それだけでは顧客の心を動かせません。
施策には必ず「顧客心理」を踏まえた設計が必要です。
例えば、休眠顧客に割引クーポンを送るだけでは動かない場合がありますが、「以前購入した商品の新モデルが登場しました」という文脈で提案すれば、ブランドへの関心や愛着を呼び起こすことができます。顧客が「自分のことを理解してくれている」と感じられる体験を提供することが、ロイヤルティ向上に活きてきます。
ポイント3:中長期的なロイヤルティプログラムの運用
CRMの成果は短期的な売上ではなく、長期的な顧客関係に表れます。そのため、会員制度やポイントプログラムを「導入して終わり」にせず、継続的に育てていく姿勢が欠かせません。
例えばステージ制や会員ランク制度を取り入れれば、購買を重ねるほどに得られる価値が増していく仕組みをつくれます。割引やポイントだけでなく、限定イベントへの招待や先行販売情報の提供といった情緒的価値を組み込むことで、「このブランドと長く付き合いたい」と思わせることが可能です。
さらに、定期的にデータを分析し、制度を顧客ニーズや市場環境の変化に合わせて見直すことで、プログラムは企業と顧客双方にとって持続的な価値を生み続けます。
実際に、いなげや様では15年以上にわたり伴走型でCRMを運用しており、ポイントカード制度の導入から購買データ分析・会員向け施策までを一貫して改善し続けています。このように「育てるCRM」の姿勢が、安定した会員プログラムの基盤となっています。
まずは現状診断からCRM成功への一歩を
小売業のCRM戦略は、単なる販促施策の集合ではなく、LTV最大化をゴールとする長期的な顧客起点の経営戦略です。STEP1で現状を棚卸し、STEP2であるべき戦略を描き、STEP3で施策を実行・改善する。この流れを組織全体で回し続けることが、顧客ロイヤルティを高め、持続的な成長へとつながります。
まずは、自社のCRMの現状を診断し、どこに課題があるのかを把握することから始めましょう。当社でご提供している 「CRM戦略スタートガイド」 には、セルフチェックシートや具体的な取り組みステップを掲載しています。自社のCRMに課題を感じている方は、ぜひダウンロードしご活用ください。
フュージョン株式会社では、30年以上にわたり、BtoCビジネスにおけるCRM戦略立案から実行支援までを一貫してサポートしてきました。
「顧客との関係性づくり」に直結する顧客戦略策定支援やデータ分析、シナリオ設計、コミュニケーション施策の実行支援まで、現実的かつ成果につながるご提案が可能です。
以下のフォームより、お気軽にお問い合わせください。


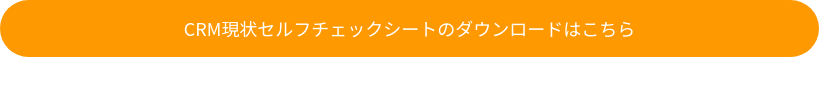
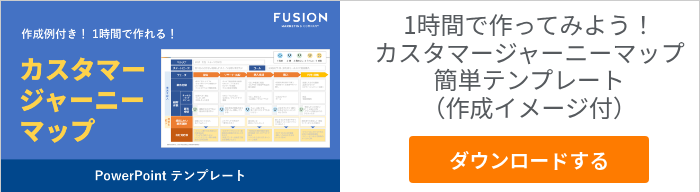

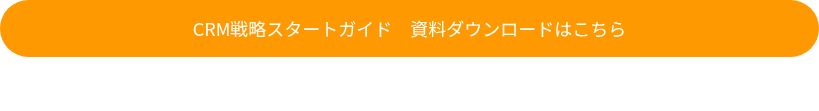
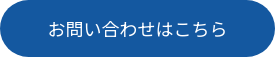


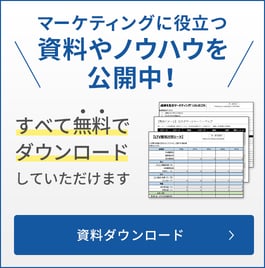



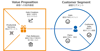




%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png?width=100&height=60&name=%E3%80%90%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BE%8B%E4%BB%98%E3%80%911%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%8B!%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(CJM)%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png)




