
顧客の購買傾向や属性に応じたコミュニケーションが重要──そう言われても、そもそも「自社にとっての顧客とは?」と立ち止まる場面は少なくありません。
フュージョンがCRM支援を行うなかでも、以下のような声を耳にすることがあります。
- 部署ごとに顧客の解釈が異なり、施策の方向性がブレる
- CRMツールを入れても成果が出ない
- メルマガやLINE配信で“セグメント”を切る判断基準が曖昧
これらの背景には、“誰を顧客とするか”という定義が社内で曖昧なまま、CRMや施策設計を進めてしまっていることがあります。
CRMは単なるツールの導入ではなく、一度でも自社の商品やサービスを購入・利用してくれた顧客との関係性の維持や顧客満足の向上を図り、売上拡大や利益向上を目指すための経営戦略のひとつです。
本記事では、そんなCRM戦略の出発点である“顧客定義”の考え方と、そのマーケティング活用についてわかりやすく解説します。
そもそも「顧客」とは誰か?マーケティング視点での考え方
マーケティングにおける「顧客」は、「すでにお金を払ってくれた人」だけではありません。
今後関係を築くべき見込み顧客や、継続的に濃い接点を持つロイヤル顧客も含めて、自社が関係を維持・育成したい対象を指します。
たとえばフュージョンが支援するBtoC企業では、以下のような顧客が対象になります。
(例)
- 商品を1回でも購入したことがあるが、リピートしていない人
- LINE登録しているが、まだ購買には至っていない人
- ポイント会員だが、休眠状態のまま1年以上接点がない人
こうした多様な接点をもつ人々を「顧客」としてどう定義し、どのように関係を深めていくかが、CRMの起点になります。
ちなみに、「客」と「顧客」は似た言葉ですが、CRMでは「顧客=企業と継続的な関係性を築く対象」として捉えることが重要です。
成功するCRMには顧客定義が必要
CRMとは、Customer Relationship Management(カスタマー リレーションシップ マネジメント)の略で、顧客関係マネジメントのことで、顧客との関係性の維持や顧客満足の向上によって売上の拡大や利益の向上を目指すための顧客志向の経営戦略であり、それに伴う手段や手法を指しています。

CRMを効果的に実施するためには、顧客定義をおこなったうえで、それぞれの顧客に必要なコミュニケーション設計や個別施策について検討する必要があります。
フュージョンでは、CRMに初めて取り組む方に向けて、よくある悩みや取り組む際のステップ、事例を紹介したお役立ち資料を公開しています。貴社の施策にご活用ください。
顧客定義とは
顧客定義とは、特定のルールで顧客をいくつかのグループに分類すること(=セグメント)、または分類するためのルールそのものを指します。
顧客は、見込み客、登録客、新規顧客、継続顧客、優良顧客、ロイヤル顧客、などいくつかのグループに分類でき、これらのグループに分類するためには、自社の顧客をよく理解し、行動や購買履歴をきちんと把握することが大切です。
どのような商品・サービスであっても、自社の顧客の属性や購買行動の傾向を的確に把握することは、顧客との中長期的な関係性を育み、LTV(Life Time Value)を最大化するために必要なステップです。
顧客定義の主なメリット
顧客を定義すること主なメリットは、2つあります。
顧客を定義することでマーケティングは“戦略”になる
顧客を明確に定義することは、マーケティング施策を感覚や経験に頼らず、“戦略”として設計するための出発点になります。
定義がないまま施策を積み重ねても、誰に向けたものかが曖昧なため、メッセージや配信タイミングにブレが生じ、効果が出にくくなってしまいます。
CRMでは、「誰に」「何を」「いつ届けるか」の精度が重要です。顧客定義は、それを支える基準軸になります。
ステージ別アプローチ設計に役立つ“ガイドライン”になる
顧客定義によって、「どの顧客に、どんなアプローチをすべきか?」の判断がしやすくなります。たとえば以下のように、ステージごとの目的に応じた対応を整理する際のガイドラインとして活用できます。
(例)
- 新規顧客に対しては:「初回購入からリピートへ引き上げる」ための、信頼形成を意識したステップ設計
- 継続顧客に対しては:習慣的な購買を妨げない自然なタイミングや提案内容の検討・実施

このように、同じ「顧客」でも、ステージによって施策の目的や打ち手は大きく異なるため、顧客定義は施策設計の指針になります。
さらに、CRM施策やキャンペーンは複数同時に走ることも多く、日々の運用において優先順位が見えにくくなる場面もあります。
そうした状況でも、明確な顧客定義を持っていれば、「今誰に注力すべきか」「この施策は何のためか」を振り返りやすくなり、チーム内の判断軸や議論のベースにもなります。
顧客をどう定義する?効果的な分類方法と考え方
顧客を定義する際は、データ分析の結果に基づいて分類ルールを設けることが基本です。
王道的な手法はいくつかありますが、正解は一つではありません。大切なのは、自社の商材特性やビジネスモデルに合った切り口で分類することです。
たとえば、定義条件として「売上金額」だけを使うのではなく、
- 購入頻度
- 購入からの経過日数
- 商品カテゴリや単価帯
なども組み合わせて検討すると、より実態に即した分類が可能になります。
RFM分析は定義づくりの代表的な方法
なかでも代表的な手法の一つが、RFM分析です。
RFMとは、以下の3つの指標で顧客を評価する方法です:
- Recency(最新購買日):最後に購入したのはいつか?
- Frequency(購買頻度):どれくらいの頻度で買っているか?
- Monetary(購買金額):いくら使ってくれているか?
これらをもとに、顧客をステージ(例:新規、継続、ロイヤル、離反予備群など)に分類することで、どの層に、どのタイミングで、どんな施策を打つべきかが明確になります。

このような顧客定義があることで、
- 今打つべき施策の優先順位
- セグメント別に適したチャネル(DM、LINE、アプリなど)
- コストをかけるべき顧客層の見極め
などを、なんとなくではなく、データに基づいて論理的に判断できるようになります。
顧客理解の鍵となる顧客分類とRFM分析の活用例を紹介
顧客定義でよくある質問(FAQ)
Q. 顧客定義とは?
A. 顧客定義とは、自社にとっての「顧客」を特定の基準で分類・明文化することです。購買履歴や接点情報などのデータをもとに、優先的に関係を築きたい対象を明確にし、CRM戦略設計の軸とするためのものです。
これは単なる分類ではなく、企業として、“誰に価値を届けるか”を意思決定する戦略的なステップでもあります。
Q. 顧客定義はどの部署が行うもの?
A. 顧客定義は、マーケティング部門が主導することが多いですが、単独で決めるべきものではありません。
販促・営業・企画・カスタマーサポートなど、“顧客と関わるすべての部署”で共通認識を持つことが重要です。
特に、施策の設計や実行部隊との認識のズレは、CRM施策の成果に直結します。
Q. RFM以外の顧客定義の方法もある?
A. はい、もちろんあります。RFM分析は代表的な顧客分析手法ですが、業種や商材によっては、商品カテゴリ、チャネル別、LTV別、心理的距離感などで定義・分類することも有効です。
大切なのは、フレームに縛られることではなく、「自社のビジネス構造や顧客特性に合った軸を見つけること」です。
Q. 顧客定義は一度決めたら固定?
A.いいえ。顧客定義は“変えてはいけないもの”ではありません。
購買傾向の変化、商材の進化、経営戦略の転換などによって、定期的な見直しが必要です。むしろ、状況が変わっても定義を変えずに使い続けてしまうと、施策のズレやCRMの形骸化につながります。
顧客定義から始めるCRM──まずは“自社の顧客”を見える化しよう
今回は顧客定義の考え方と重要性について解説しました。顧客定義は、CRMを単なるツール導入ではなく、顧客との関係性を深める“戦略”へと進化させる鍵です。
施策の優先順位、伝えるメッセージ、注力すべき顧客──
そのすべてを支えるのが、「自社の顧客をどう定義するか」です。顧客定義は、CRM戦略のスタート地点ですが、戦略全体の設計を考えるには「全体の流れ」を理解しておくことも重要です。詳しくは以下の記事でも解説していますので、あわせてご一読ください。
フュージョンでは、CRMを初めて取り組む方にもご活用いただける資料や、顧客構造の可視化支援を行っています。
自社のCRMを見直す第一歩として、ぜひお役立てください。


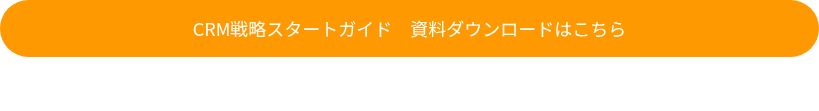

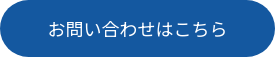


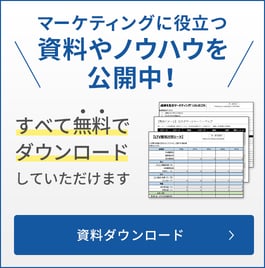



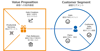




%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png?width=100&height=60&name=%E3%80%90%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BE%8B%E4%BB%98%E3%80%911%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%8B!%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97(CJM)%E2%94%82%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.png)




